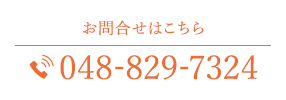生活習慣病について
 生活習慣病は食事や運動、飲酒、喫煙、ストレスなどの生活習慣、遺伝によって発症・悪化する疾患の総称です。自覚症状がほとんどないまま、徐々に動脈硬化を進行させ、脳卒中や心筋梗塞などの重篤な疾患を引き起こすリスクがあります。そのため、早期に発見し、状態に応じた治療や生活習慣の見直しを行うことが必要です。
生活習慣病は食事や運動、飲酒、喫煙、ストレスなどの生活習慣、遺伝によって発症・悪化する疾患の総称です。自覚症状がほとんどないまま、徐々に動脈硬化を進行させ、脳卒中や心筋梗塞などの重篤な疾患を引き起こすリスクがあります。そのため、早期に発見し、状態に応じた治療や生活習慣の見直しを行うことが必要です。
当院では以下の内容を伺い、その上で効果が高く無理なく続けられる生活習慣の改善指導を行います。
- 食事:1日の食事回数・時間・内容
- 運動:1日の運動時間・内容
- 睡眠:就寝時間・睡眠時間・睡眠の質
- 嗜好品:喫煙・飲酒の回数や量
- ストレス:内容・対処法
高血圧
高血圧とは
心臓は繰り返し拡張・収縮することで全身に血液を届けます。高血圧は拡張期血圧が90mmHg以上、もしくは収縮期血圧が140mmHg以上またはその両方が該当する状態です。血圧は食事や動作、気分などで変化しますので、1回の計測のみで高血圧と診断することはありません。安静時に基準値を上回った状態が繰り返し計測される場合に診断されます。
高血圧が慢性化すると血管壁に大きな負担がかかり、動脈硬化を進行させます。なお、自覚症状がないことが多く、気付かないうちに心疾患や脳血管疾患などの重篤な疾患が起きていることもあります。動脈硬化の進行を防ぐためにも、早い段階で適切な治療を受け、血圧の良好な状態を維持することが必要になります。
目標血圧
目標血圧は患者さんの年齢や基礎疾患の有無などによって変わります。
| 75歳未満 | 診察室血圧:130/80mmHg未満、家庭血圧:125/75mmHg未満 |
|---|---|
| 75歳以上 | 診察室血圧:140/90mmHg未満、家庭血圧:135/85mmHg未満 |
| 腎臓慢性疾患(尿蛋白陰性)がある | 140/90mmHg未満 |
| 糖尿病や脳血管障害がある | 130/80mmHg未満 |
※血圧は環境の変化で変わりやすいです。緊張しやすい診察室では高めに出やすく、リラックスできる家庭では低めに出る傾向があります。そのため、それぞれの目標数値が設定されています。
高血圧の原因
高血圧は、食事や運動などの生活習慣、ストレス、遺伝などが関与します。そのため、高血圧の改善・予防には生活習慣の見直しが欠かせません。
生活習慣が原因で高血圧が起こっている場合は、脂質異常症や糖尿病などの生活習慣病を併発する可能性があります。特に、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満があり、血圧・血糖・脂質のうち2つ以上が基準値を上回る状態)の方は特に動脈硬化の悪化を招きやすいことが判明しているため、注意が必要です。
動脈硬化、高血圧、糖尿病、脂質異常症は自覚症状がほとんどなく、動脈硬化を進行させ、脳卒中や心筋梗塞などの重大な病気の発症リスクを上昇させます。そのため、健康診断で異常が出た場合はお早めに当院までご相談ください。
稀に他の病気や服用中のお薬がきっかけとなり高血圧が起こることがあります。その場合は原因疾患に対する治療やお薬の変更を行うことで改善が期待できます。
高血圧の治療
主に生活習慣の見直しを行います。体重を適正値にする、軽い有酸素運動を習慣化する、塩分を制限する、禁煙・禁酒を心掛ける、休息や睡眠時間を十分に確保するなどが大切です。
動脈硬化の進行を防ぐために目標血圧にコントロールしていきましょう。生活習慣の改善は続けることが重要なので、無理なく続けられる内容にする必要があります。また、治療を早い段階から取り組むことで、生活の制限が軽いものでも十分に効果を発揮します。血圧が基準値以上の場合、早めに当院をご受診ください。
患者さんの状態に応じて、生活習慣の改善のみでは十分な治療効果が期待できない場合は薬物療法も取り入れた治療を行います。
糖尿病
糖尿病とは
 血液に含まれるブドウ糖は全身の細胞のエネルギー源です。血糖値は血中のブドウ糖濃度を示す値で、食後は一時的に高くなりますが、膵臓のβ細胞で作られるインスリンの働きでブドウ糖が細胞内に取り込まれることで、適正値を保っています。
血液に含まれるブドウ糖は全身の細胞のエネルギー源です。血糖値は血中のブドウ糖濃度を示す値で、食後は一時的に高くなりますが、膵臓のβ細胞で作られるインスリンの働きでブドウ糖が細胞内に取り込まれることで、適正値を保っています。
糖尿病は、インスリンの作用または分泌が低下することで、ブドウ糖が細胞内に取り込まれなくなってしまい、慢性的に高血糖になる疾患です。動脈硬化の進行を招き、脳卒中や心筋梗塞などの重篤な疾患に繋がる可能性があります。また、毛細血管にダメージを与え続け、重大な合併症を発症する恐れもあります。
糖尿病のタイプ
糖尿病は1型糖尿病と2型糖尿病に分類され、そのうち全体の95%程度を2型糖尿病が占めます。
1型糖尿病は、感染症などが原因となり膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンが作られなくなることで起こります。
一方、2型糖尿病は遺伝や生活習慣の乱れなどが原因で発症すると考えられており、インスリンの分泌・作用が低下することで起こります。
糖尿病の合併症
高血糖は血管に負担をかけ続けるため、全身の動脈・静脈・毛細血管にも大きなダメージを与え、重大な合併症を引き起こす可能性があります。
糖尿病特有の合併症は複数ありますが、代表的なものとして、下肢の切断の危険性がある「糖尿病神経障害」、失明の危険性がある「糖尿病網膜症」、悪化した場合は人工透析を行う必要がある「糖尿病腎症」があり、これらをまとめて糖尿病の3大合併症と言います。糖尿病網膜症は、眼科の定期検診が必要になりますので、糖尿病を発症した場合、内科と併せて眼科も定期的に受診しましょう。
糖尿病の治療には生活習慣の改善が欠かせませんが、これは様々な合併症予防にも繋がります。血糖値のコントロールのため、当院では患者さんそれぞれの状態、生活習慣に合わせたサポートを行っています。
糖尿病の治療
1型糖尿病
インスリンが分泌されない状態のため、インスリン注射が必要です。患者さんの状態に応じて、超速効型インスリンと持効型インスリンを使用します。また、自己血糖測定を行い、患者さんご自身でも血糖値を把握して、適正値にコントロールすることが重要です。
2型糖尿病
減量と適正体重キープ
肥満の方は、適正体重を目標にカロリー制限に取り組みます。栄養バランスの整った食事を適量、できるだけ同じ時間帯に食べるようにしましょう。減量効果は一気に感じることはなく、効果が出るまで継続することが大切です。なお、無理をしてしまうと続かないので、負担があまりかからない程度から取り組んでいきましょう。当院では、患者さんの食事の好み、生活習慣などをもとに、適切な食事指導を実施しています。お気軽にご相談ください。
運動療法
習慣的な運動で全身の血流が改善し、細胞のブドウ糖吸収率が良くなることで、血糖値の改善が期待できます。また、筋肉量が上がり代謝が活発になると、インスリンの作用も向上します。運動はきついものである必要はなく、軽めの有酸素運動を1日30分、週に3回以上を目安に行うと良いでしょう。
薬物療法
糖尿病の薬には様々な種類があります。また、同じ薬を使用しても、患者さんの状態によって効果や副作用の程度も異なります。当院では、患者さんの状態、生活習慣、既往歴、服用中のお薬などをお伺いした上で、適切なお薬を選択します。また、再診の際に患者さんの状態をお伺いし、処方内容を調整しております。服用の時間を毎日合わせることができない、飲み込みづらさを感じるなど、お薬についてお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
脂質異常症
脂質異常症とは
脂質異常症は、血中のコレステロールや中性脂肪などの脂質が基準値を外れた状態が慢性化した状態です。血中を流れる脂質は、HDL(善玉)コレステロール、LDL(悪玉)コレステロール、中性脂肪(トリグリセライド)などがあります。このうち、LDLコレステロールと中性脂肪が基準値を上回る状態が高脂血症です。HDLコレステロールは血中の過剰になった脂質を回収して肝臓に運ぶ役割を持ち、この脂質が減ってしまうと動脈硬化の進行を招きます。脂質異常症はこうした状態の総称です。
脂質異常症の原因
脂質異常症の原因は、暴飲暴食や偏食、運動不足、肥満、飲酒、喫煙、ストレスなどの生活習慣の乱れ、遺伝などが関与して発症すると言われています。内臓脂肪型肥満がある場合、LDLコレステロールや中性脂肪が過剰に増えるのに対し、HDLコレステロールが低下しやすく、この状態に高血圧や糖尿病を合併すると、数値がさほど高くない場合も動脈硬化が悪化しやすいことが判明しています。
遺伝が原因となる家族性高コレステロール血症は、LDLコレステロールが高値を示し、若い頃から動脈硬化が進行することで、血管の狭窄・閉塞が起こります。心臓の血管に大きく影響し、狭心症や心筋梗塞を招く恐れもあります。300人に約1人発症すると言われており、動脈硬化の進行スピードが早いので、早期発見が欠かせません。健康診断で脂質の異常を指摘された時には、お早めに当院までご相談ください。
脂質異常症の治療
食事療法と運動療法を中心に行い、適正体重を維持することが必要です。なお、どの脂質が異常を示しているかに応じて治療内容が変わります。こうした治療を継続することで動脈硬化の進行を防ぐことができます。医師の指示に従って無理のない範囲で続けましょう。
脂質異常症は悪化あるいは改善しても自覚症状が乏しい特徴があります。そのため、状態に応じた治療を受けるためにも定期的な受診が欠かせません。食事療法と運動療法のみでは効果が十分でない場合、薬物療法も行います。
高尿酸血症(痛風)
高尿酸血症(痛風)とは
 高尿酸血症は、慢性的に尿酸値が高い状態です。血液中の過剰な尿酸が結晶になり関節に溜まり、炎症を起こしたものが痛風です。なお、高尿酸血症であっても痛風の症状が出ないこともあります。ただし、尿酸値の高い状態は腎臓の機能低下や尿路結石を招き、将来、脳卒中や心臓疾患発症のリスクが高まることが知られています。そのため、健康診断で尿酸値の異常を指摘された場合は早期に適切な治療を行うことが大切です。
高尿酸血症は、慢性的に尿酸値が高い状態です。血液中の過剰な尿酸が結晶になり関節に溜まり、炎症を起こしたものが痛風です。なお、高尿酸血症であっても痛風の症状が出ないこともあります。ただし、尿酸値の高い状態は腎臓の機能低下や尿路結石を招き、将来、脳卒中や心臓疾患発症のリスクが高まることが知られています。そのため、健康診断で尿酸値の異常を指摘された場合は早期に適切な治療を行うことが大切です。
高尿酸血症の原因
高尿酸血症は、尿酸の過剰な産生、排出が十分でないことが原因です。リスク因子としては、代謝異常、腎機能低下、プリン体の摂取、飲酒、水分不足、遺伝などが挙げられます。
痛風発作について
痛風発作が起きると、尿酸が溜まった関節が赤く腫れあがり、激しい痛みを伴います。この症状は数日~2週間程度で解消します。症状は足の親指に起こることが多く、痛みが強く歩けなくなることもあります。
痛風発作が起きている期間は、血液検査を行っても尿酸値を正確に測定することができないため、まずは痛みや炎症を緩和し、その後に検査を行い、高尿酸血症の治療を実施します。また、尿酸値が目標値まで下がっても、結晶化した尿酸が排出されるまで治療を継続する必要があります。激しい運動は痛風発作を誘発する可能性があるため、注意が必要です。
高尿酸血症の治療
血液検査で血清尿酸値が7.0mg/dL以上と判定された場合は治療が必要です。まずは生活習慣の改善を行います。プリン体が豊富な食品やアルコールの摂取は控え、水分をしっかり補給しましょう。それでも効果が不十分な場合は薬物療法を行います。痛風発作が起きた場合は、最初から薬物療法を行うこともあります。なお、急激な尿酸値の変化は痛風発作を起こす可能性があるため、徐々に下げていくことが必要です。